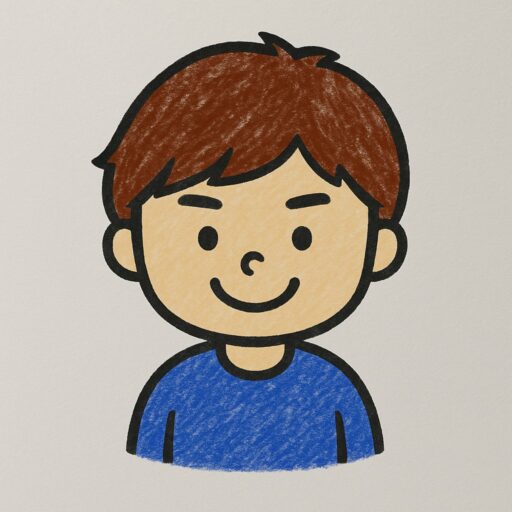実はタイタニック号での事故で、お酒を飲んでいたから助かったと言われる人物がいる事をご存知ですか?
そんな奇跡のような話を今回は紹介します。
えっ、飲んでたら助かった?

1912年、北大西洋に沈んだ豪華客船タイタニック号。
1,500人以上が命を落とした大事故の中、ある“酔っぱらい”だけが奇跡的に生還した――。
その人物の名は、チャールズ・ジョフィン(Charles Joughin)。
パン職人長として乗船していた彼は、冷静にブランデーをあおり、氷点下の海に飛び込み、生き延びたのです。
しかも、約2時間ものあいだ、マイナス2度の冷水に浸かりながらも、低体温症に陥らず生還。
この話、にわかには信じがたいですが、実は科学の視点から見ても、完全な“与太話”とは言えません。
“飲んだくれサバイバル” チャールズ・ジョフィンとは?
- 職業:タイタニック号のチーフ・ベイカー(パン職人長)
- 年齢:当時33歳
- 特徴:がっしりした体格、責任感が強く、沈没直前までパンを焼き、乗客へ配っていたという逸話も
沈没が迫る中、彼は船内に残り、大量のブランデーを飲んだあと、海に飛び込んで救助を待ち続けたと証言されています。
なぜ“酔っぱらい”が助かったのか?科学でひも解く5つの理由

1. アルコールの鎮静効果でパニックを回避?
酔うことで恐怖や不安を抑える効果があり、極限状態での過呼吸や無謀な行動を防いだ可能性があります。
ジョフィンも「寒さは感じたが、恐怖はあまりなかった」と語っています。
出典:CDC「Alcohol and Cold Exposure」
2. 血管拡張作用で“凍死”を回避?
アルコールは血管を拡張し、末端の血流を一時的に維持します。
その結果、手足の動きが保たれ、泳ぐことができた=溺死を回避できたと考えられます。
ただし、これは一時的。基本的に飲酒は低体温を招くため、一般的には危険行為です。
3. 体格が良かった=断熱効果あり?
ジョフィンは当時の証言や記録から、比較的がっしりとした体型だったと推測されています。
脂肪量が多いほど体熱を保持しやすく、低体温症への耐性が高くなるとされています。
4. 動き続けたことで体温をキープ
救助されるまでの2時間、彼はほとんどの時間を泳ぎ続けていたと記録されています。
動くことで血液循環が促進され、体温の低下を遅らせた可能性が高いです。
5. 最終的に「水に浸からなかった」ことが決め手
沈没後、彼はB号救命ボートの側面にしがみついていたことが生還の決定打に。
完全に水没せず、部分的に身体が水面に浮いていたことで、低体温症の進行を防ぎました。
⚠️ 注意:「酔って助かった」は奇跡の例外
医学的には、飲酒と低体温症は非常に危険な組み合わせです。
- 血流は良くなるが体温は奪われやすくなる
- 判断力が鈍り、動けなくなるリスクが高まる
- 基本的には「酔って助かる」なんてことは、ありえない
ジョフィンの生還は「たまたま全てがうまくかみ合った」奇跡の化学反応だと言えるでしょう。
ジョフィン生還の科学的要因まとめ
| 要因 | 効果 |
|---|---|
| アルコールによる鎮静作用 | 恐怖を抑え冷静さを維持 |
| 血管拡張 | 四肢の血流が保たれ溺死回避 |
| 体格の良さ | 体温保持に有利 |
| 泳ぎ続けたこと | 循環促進・体温低下を遅延 |
| 救命ボートにつかまった幸運 | 水中から一部脱出・体温維持 |
まとめ|ジョフィンの奇跡が私たちに教えてくれること
お酒のせいで助かった?
確かに、そう見えるかもしれません。
でも実際は、
- 冷静さ
- 行動力
- 体力
- 運
全てが合わさった「確率0.1%の奇跡」だったのです。
さいごに|歴史の小さな物語に、科学の光を
ジョフィンのエピソードは、映画のようなストーリーですが、科学的な視点で紐解くことで、より深い学びがあります。
「酔っぱらいが助かった」という雑談ネタの裏には、
人間の極限状態、医学、心理、環境などが交差した壮大なドラマがあるのです。
次にお酒を飲むとき、ふとこの話を思い出してみてください。
そして――
くれぐれも真似しないでくださいね。
それではこの辺で、ほいたらねっ👋
関連記事
【未来都市】Dogen Cityとは何か?海上に浮かぶ“現代のノアの箱舟”構想を徹底解説|ワンピースの「ウォーターセブン」は現実になるのか?
あなたの“信じる力”を試す物語|ジョニー・デップを支えたディオールと復活の真実
【保存版】今もっとも売れているレゴTOP3|科学が証明する“遊びの価値”とおすすめポイントを徹底解説!