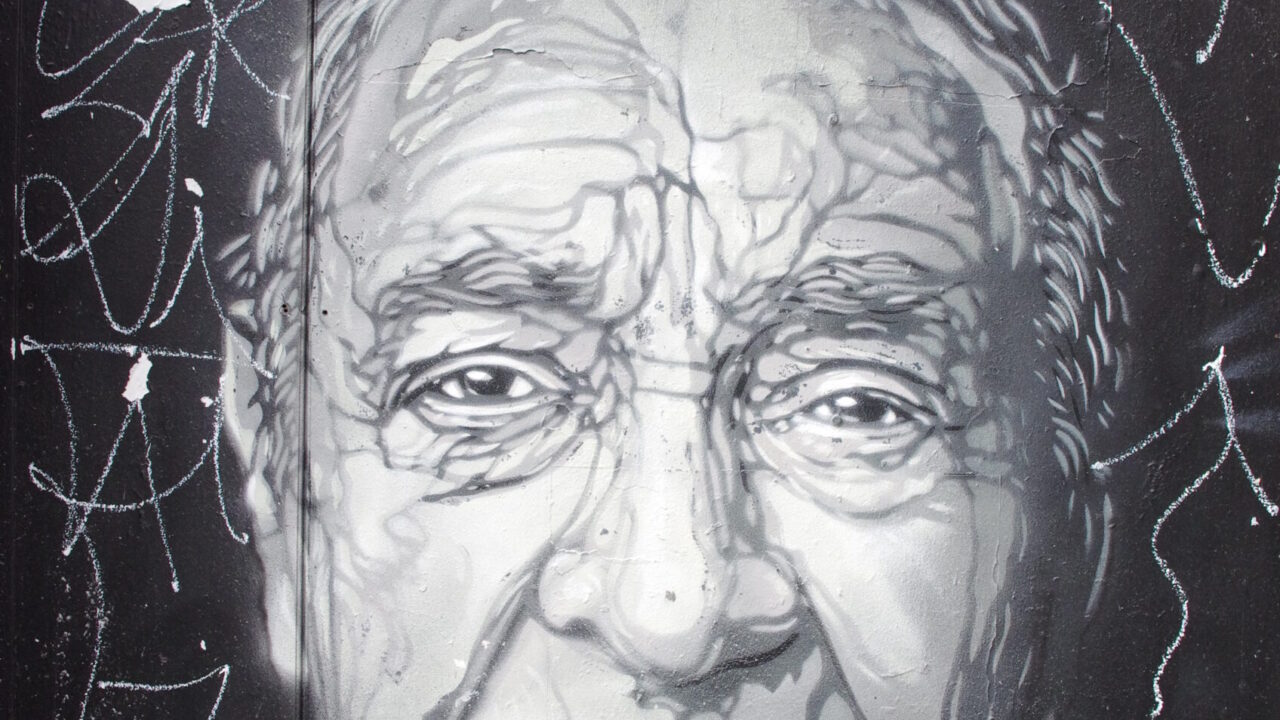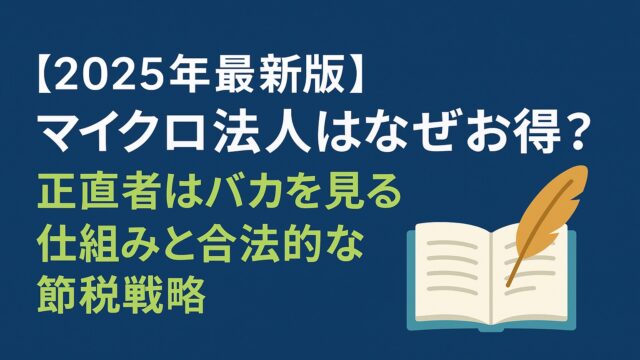私の保険に対しての考え
私は基本的に保険は不要という考えです。
必要なのは自動車保険、火災保険、生命保険だけだと考えています。
保険は何かあった時のために、生活が困窮してしまうような大きな損害にだけ掛けたので十分です。
自動車保険について
自動車保険は『対人対物に対して無制限に保険をかける』そこは重要がだと思います。あって欲しくありませんが、もし事故を起こした時にとても責任をおえるものではなく、生活も崩壊する恐れがあるためです。
自動車保険(対人賠償保険)に入っていれば、原則としてお金の問題はカバーされます。
具体的には、
- 慰謝料
- 治療費・葬儀費用
- 遺族への損害賠償金(失われた将来収入の補償など)
これらを保険会社が支払うことになります。
しかも最近の自動車保険では、
- 「無制限」で対人賠償できる契約がほとんどです。
だから、金銭的に「自分の私財ですべてを支払わなければならない」という状況には、
通常はなりません。
ただし、
- 重過失(たとえば飲酒運転、無免許運転など)がある場合
- 故意に事故を起こした場合
これらに該当すると、保険が支払われない、あるいは保険会社に「求償」(後から支払金を請求される)されることもあります。
交通事故は保険で金銭的に負担をカバーされても、失われたものは戻ってくることはありません。相手家族や世間的にも非難を浴びせられるでしょうがどうすることもできないでしょう。
そもそも交通事故を起こさないということを心がけましょう。
火災保険について
火災保険については、マイホームにしても賃貸にしても家と言うものは何かあった時に何度も立てれるようなものではありません。
マイホームの場合は、人生最大の買い物になる人がほとんどだと思います。家を失い、もう一度立て直すと言うことはほどんどの人の場合不可能です。賃貸も同様でアパートなどであれば億を超えるような損害があるかも知れません。
火災で家を失うと、保険を掛けていなければ損害はかなり大きいものにな入ります。
火災保険でカバーできる主なもの
1. 火災
- 火事による建物や家財の損害を補償します。
- 近隣からのもらい火でも補償されます。
2. 落雷
- 雷による建物や家電製品の破損(例:落雷でテレビが壊れるなど)。
3. 破裂・爆発
- ガス漏れなどによる爆発事故による損害も対象です。
4. 風災・雹災・雪災
- 台風・強風・雹(ひょう)・大雪などによる
屋根の破損や壁の損壊、窓ガラスの破損なども補償します。
5. 水災
- 大雨や台風による洪水・土砂崩れで、建物や家財に被害が出た場合もカバーされることがあります(ただし契約によっては水災を外している場合もあるので注意)。
6. 盗難
- 空き巣被害による家財の盗難や破損(例:窓ガラスを割られて侵入されたなど)。
7. 水濡れ
- 上階からの水漏れ事故(洗濯機や風呂からの漏水)による損害も対象になることがあります。
8. 建物外部からの物体落下・飛来
- 飛んできた看板や樹木などで家が壊れた場合など。
9. 騒じょう・集団行動に伴う暴力行為
- デモや暴動で家や店舗が破壊されたときの損害もカバーされることがあります。
【自分の家が原因で火災が起き、お隣さんが亡くなった場合】
ここで疑問に思ったことを調べたので紹介します。
まず基本的なルール
日本には「失火責任法」という法律があります。
この法律では、
自分の家から出た火災でも、重大な過失(=かなりひどい注意不足)がない限り、賠償責任を負わない
と定められています。
つまり、
普通の不注意(たとえば、鍋を火にかけたままうっかり寝てしまった)くらいでは、
法律上、お隣さんに賠償金を支払う義務はないのです。
これは、昔の日本の木造住宅文化(火が燃え広がりやすい)を背景に、
「火事を出した人を過度に責めない」という考え方からきています。
火災保険はどうなるか?
火災保険は基本的に「自分の家・家財の損害」を補償する保険です。
つまり、
- 自分の家や持ち物が燃えた場合 → 自分の火災保険から補償
- お隣さんの損害 → 自分の火災保険では基本的にカバーされない
となります。
じゃあお隣さんは泣き寝入りなのか?
お隣さんが自分で火災保険に加入していれば、
そのお隣さん自身の火災保険から補償を受けることになります。
(つまり、自分で自分の損害をカバーするイメージです)
重大な過失がある場合は別
もし、
- コンロの火をつけたまま外出してしまった
- 暖房器具の危険な使い方をしていた
など、
重大な過失が認められた場合は、
例外的に、賠償責任を負うことになります。
この場合に備えて、
火災保険に付帯できる「個人賠償責任保険」や「類焼損害補償特約」などをつけておくと、
自分の過失で他人に損害を与えた場合の賠償金をカバーできます。
生命保険について
生命保険については、養うべき家族や子供がいた場合のみ必要という考えです。
まずマイホームを持っていた場合は、私が亡くなった時には団信でローンはなくなります。それだけでも妻の住むお家に対しての負担は大きく減るでしょう。仕事はしてもらわないといけませんが、住むお家の負担が少なければ生活する事はできると思います。
子供がいる場合の学費や生活費については、国の公的保険である程度カバーする事ができます。
遺族年金では、妻と子供1人の場合ざっくり最大1800万円カバーできるという計算です。
それでも足りない部分に対してだけ保険を掛けましょう。
個人的には、子供が成人または自立すれば生命保険は不要という考えです。
1. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
あなたが亡くなったとき、妻や子どもには「遺族年金」が支払われます。
遺族年金には2種類あります。
| 名称 | もらえる条件 | 支給対象 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金の加入者だった場合 | 18歳未満の子どもがいる配偶者 or 子ども本人 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた場合 | 配偶者・子ども・父母・孫など(優先順位あり) |
つまり、
あなたが会社員や公務員だった場合は、**「基礎年金」+「厚生年金」**のダブルでもらえる可能性があります。
2. 労災保険(仕事中や通勤中に亡くなった場合)
仕事中や通勤中の事故で亡くなった場合は、
労災保険から遺族補償年金や一時金が支払われます。
(ただし、これは通常の死亡の場合とは別枠なので、ここでは一旦除外しておきます)
【遺族年金で実際にもらえる金額のイメージ】
おおまかな金額をざっくりお伝えすると、
【遺族基礎年金】
- 年額 約 80万円+子ども加算(子ども1人につき加算あり)
- 子ども1人の場合 → 約 100万円くらい
- 子ども2人ならもう少し増えます。
※支給されるのは「子どもが18歳になる年度末まで」です。
【遺族厚生年金】
- 亡くなった人の生涯平均年収の約2割くらい
- たとえば、年収500万円の人なら → 遺族厚生年金は年間約50~60万円くらい
(※ざっくり計算なので実際は加入期間や保険料納付状況によって違います)
しかも、配偶者(特に妻)が「40歳以上65歳未満」なら「中高齢寡婦加算」(年額 約58万円くらい)も加算されます。
まとめ
個人的必要な保険は、自動車保険、火災保険、生命保険の三つです。
その他、学資保険などであれば積立nisaで運用する方が良い、私が亡くなった時に関しては生命保険で備えるという考えです。
医療保険についても、国の公的保険の高額医療制度などである程度カバーできると思っています。足りない部分については貯金で備えましょう。
そもそも保険はもし何かあったときに生活が困窮するような損害が大きなものに対してだけ掛けましょう。
保険はパチンコのようなものです。得をする人もいれば損をする人もいる。そして多くの人が損をするということ。そうでなければ保険は成り立ちません。
あなたがパチンコを辞めた方が良いと言う人であれば、自分の入っている保険についても見直してみましょう。