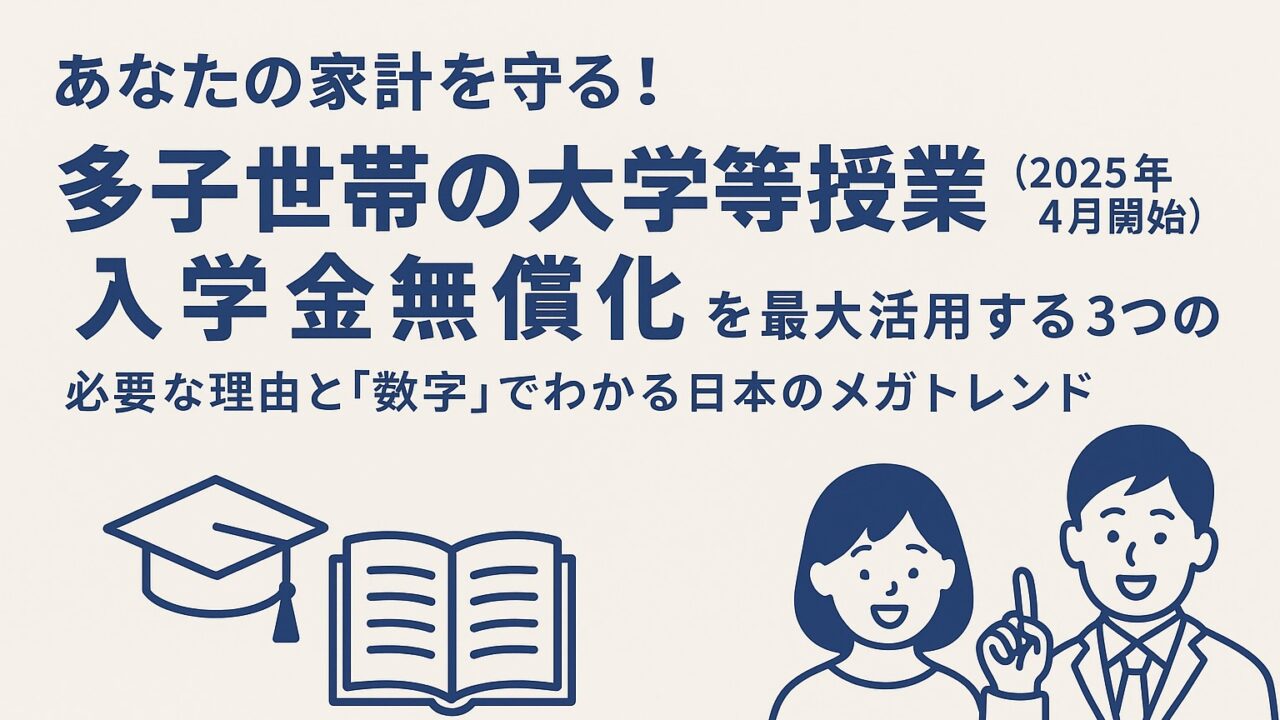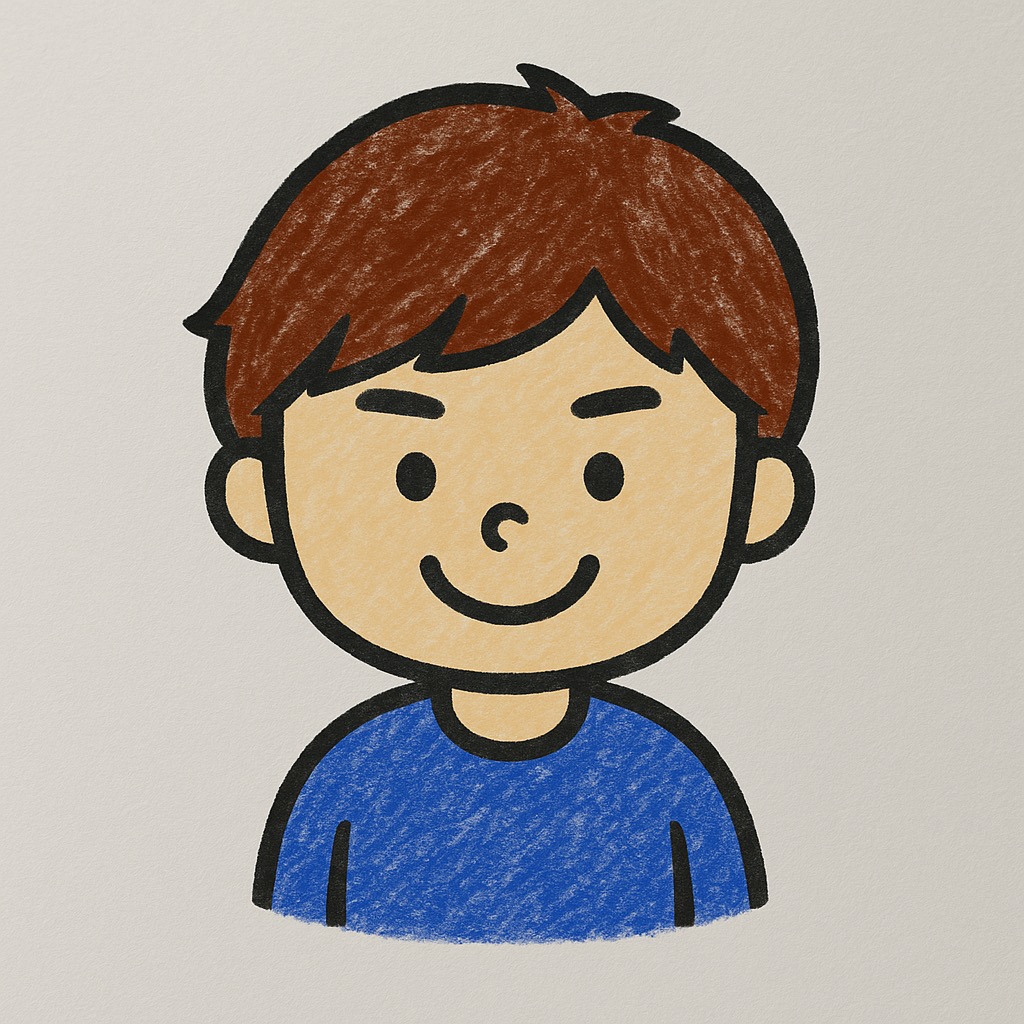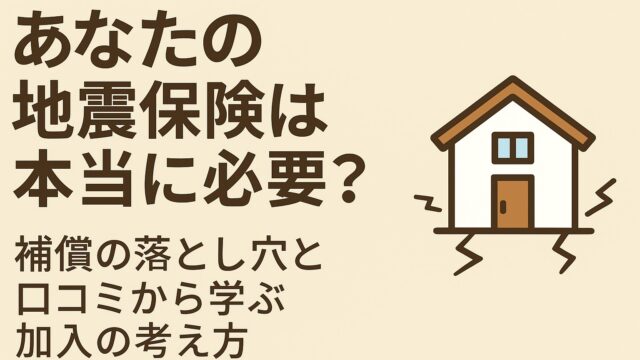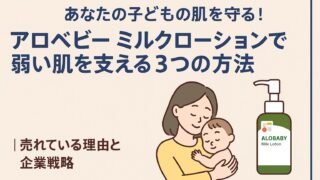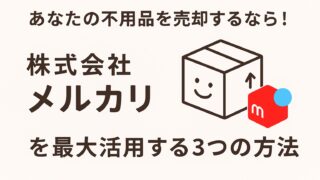今回は日本の人口減少に少しでも歯止めをかける制度について紹介します。
はじめに|「学びをあきらめない」を家計から後押し
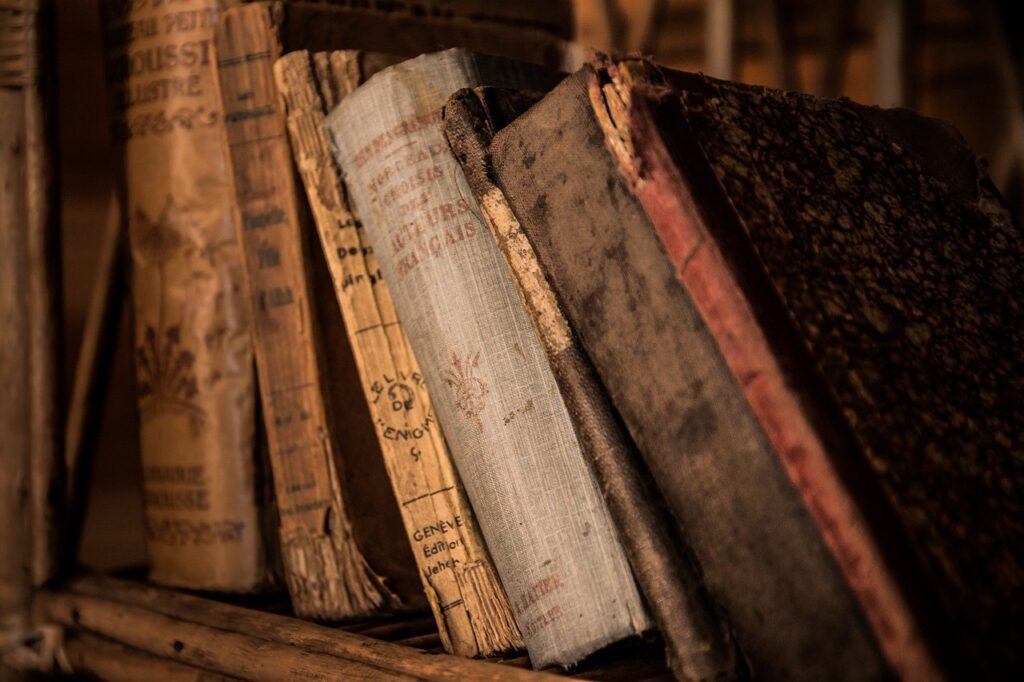
2025年4月(令和7年度)から、扶養する子どもが3人以上の世帯(多子世帯)について、所得制限なく大学・短大・高専(4・5年)・専門学校の授業料・入学金が国の定める上限額まで無償(減免)になります。既入学の2〜4年生も対象(条件あり)です。
これは、文部科学省が発表した「高等教育の修学支援新制度」拡充の一環で、教育費負担の軽減と出生率低下の歯止めを同時に狙う政策です。
1. 制度の要点
対象
- 同時に3人以上を扶養している世帯の学生(前年12月31日時点)
- 対象校は、国の要件を満たす大学・短大・高専・専門学校
減免内容(上限額)
| 学校種別 | 国公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 大学 | 入学金 28万円/授業料 54万円 | 入学金 26万円/授業料 70万円 |
| 短期大学 | 入学金 17万円/授業料 39万円 | 入学金 25万円/授業料 62万円 |
| 高専(4・5年) | 入学金 8万円/授業料 23万円 | 入学金 13万円/授業料 70万円 |
| 専門学校 | 入学金 7万円/授業料 17万円 | 入学金 16万円/授業料 59万円 |
※金額は年額。入学金は初回のみ。学部・課程により変動あり。
例:私立大学(年間授業料150万円)の場合、最大70万円が減免され、差額80万円+入学金の差額を自己負担。完全無料ではないことに注意。
その他の条件
- 所得制限なし(ただし資産合計3億円未満など資産要件あり)
- 成績・学修状況で支援停止の可能性あり
- 2025年度は「在学採用」のみ(入学後に学校経由でJASSO申請)
2. 対象になるための条件と注意点

条件
- 前年12月31日時点で3人以上が扶養に入っている
- 全員が大学・短大・高専・専門学校に在籍し、制度要件を満たす
- 進学・卒業・就職が重ならず扶養人数が減らない
対象外のパターン
- 年子でないため、同時在学が3人にならない
- 上の子が卒業・就職で扶養外になる
- 高校生や留学生はカウントされない
現実的な可能性
統計的には、3人全員が同時に対象になるケースはまれ。実際は「2人対象」や「一部のみ」が多くなると予測されます。
3. あなたにできる3つの方法(家計インパクトを最大化)
- 上限額を把握する
学校種別ごとの上限(例:私立大 授業料70万円/入学金26万円)を確認し、差額や生活費を見込んだ家計計画を立てる。 - 扶養タイミングを調整
年末時点で3人以上が扶養に入るように、進学・就職スケジュールを家族で戦略的に計画。 - 申請を確実に行う
支援は自動適用ではないため、学校窓口経由でのJASSO申請を忘れない。締切厳守。
4. この制度が必要な3つの理由

- 家計負担を年間50〜100万円軽減
私立大学で上限満額適用なら、授業料70万円+入学金20〜26万円が免除され、進学期の経済的負担が大幅に減る。 - 人口減少にブレーキ
日本の人口は2024年時点で年間▲55万人減、日本人だけで見ると▲89.8万人減=「県が1つ消える」規模。進学支援は出生率維持の一因となる。 - 公平で形のある支援
所得制限撤廃で中間層にも届き、教育格差の縮小に寄与。
5. 数字で見る日本のメガトレンド:人口減少と外国人増
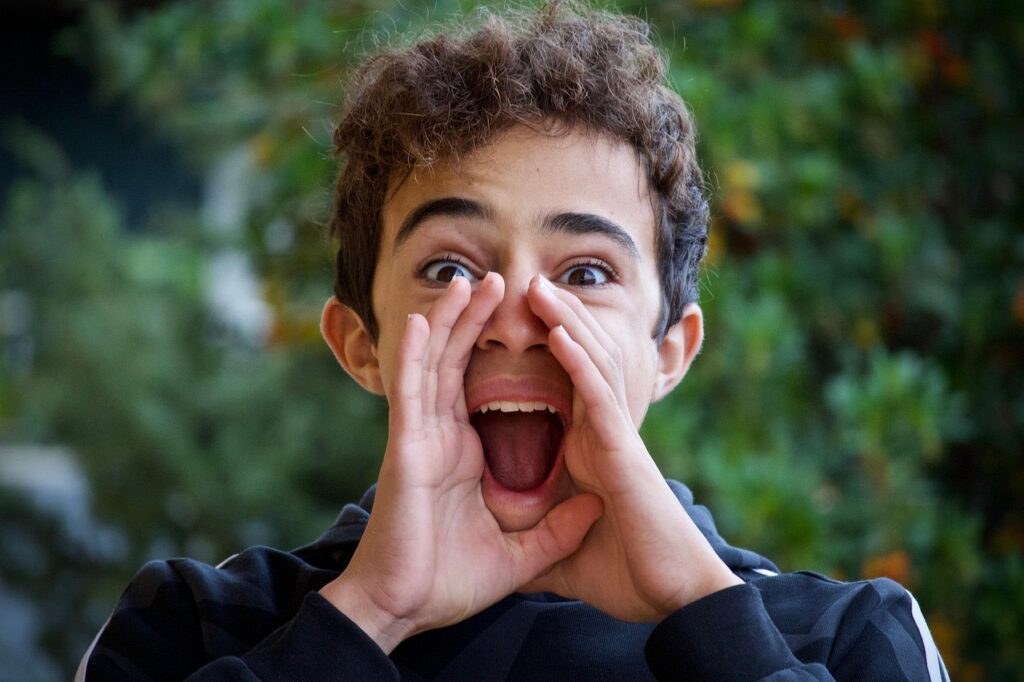
- 人口減少:総人口▲55万人/年、日本人▲89.8万人(過去最大)
- 外国人増:2024年末在留外国人約377万人(前年比+10.5%)=人口比約3%台
ここを誤解しない
- 外国人増=悪ではない。労働力補完、多文化交流、地域活性化などプラス面も大きい。
- 犯罪率は国際的に低水準。人口比で見ても日本人と大差ない。
- 課題は文化・価値観の違いと、経済的困窮層の増加による一部治安悪化リスク。
結論
日本人の出生・進学・就業支援と、多文化共生の両立が今後の国力維持に不可欠。
6. まとめ|「3人目の教育不安」を減らし、日本の未来を支える
この無償化制度は、教育費負担軽減と少子化対策の両面で効果が期待される政策です。もちろん、これだけで人口減少が止まるわけではありません。賃上げ、子育て費用のさらなる補助、働き方改革など、総合的な取り組みが必要です。
しかし、「3人以上の子どもを育てる家庭が、安心して高等教育を受けさせられる」という環境づくりは、日本の未来に向けた確かな一歩です。
あなたの家計を守り、子どもの学びを支えるために、この制度を最大限活用していきましょう。また、選挙へ行って良い国になるよう私達にできることをしましょう。
それではこのへんで、ほいたらねっ👋