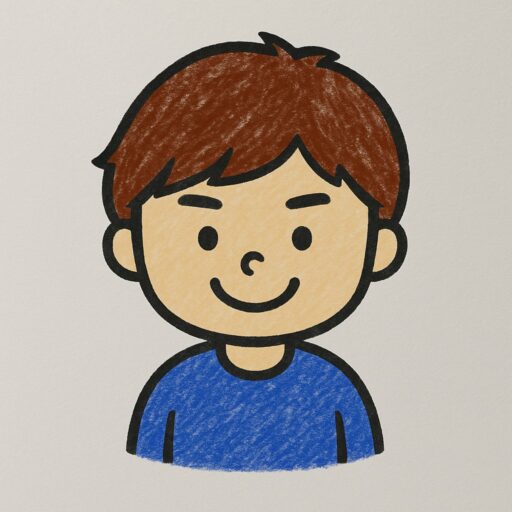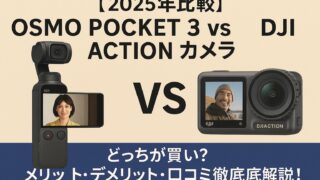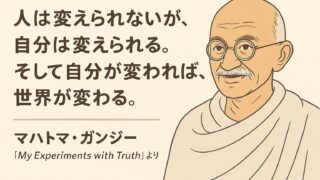税金を払いすぎてなかなか貯金が余らない、そんな悩みを抱えていませんか?
今回は事業を持つことで、支払う税金を減らせる驚きの理由を紹介いたします。
はじめに:私が“税金”を学ぼうと決めた理由
私は現在、義父から引き継いだ自営業(水道リフォーム業)に挑戦しています。同時に、副業としてブログやアフィリエイトにも挑戦中です。
なぜそんなにも忙しい中で副業に挑むのか?
その答えのひとつは、「合法的に税金を抑えて、家族を守るお金を増やしたい」という強い想いにあります。
節税を学ばなければお金は残らない現実
「もっと稼がなきゃ」「もっと節約しなきゃ」と思っていた私ですが、お金が思ったよりも貯まらない…そんな現実がありました。
その原因のひとつが「税金と社会保険料」の重さ。
そしてある日、気づいたのです。
「税金の仕組みを知らない限り、いくら稼いでもお金は貯まらない」と。
実例比較:個人と法人で「100万円を得て50万円使ったら」どうなる?
ここで、わかりやすく個人と法人の税金の違いを数字でシミュレーションしてみます。
■ サラリーマンの場合
- 収入:100万円
- 経費(私的な消費):50万円(※個人の生活費なので経費にはならない)
- 課税所得:100万円
約30%前後が税金・社会保険料としてかかります。
(所得税・住民税・国民健康保険など)
- 税金:約30万円
- 残り:70万円 → 50万円消費 → 貯金できるのは20万円
✅ サラリーマンは、「使ったお金に税金がかかる」という仕組みです。
■ 事業主(会社経営)の場合
- 収入:100万円
- 経費(事業として消費):50万円(※出張・広告費・機材購入など)
- 課税所得:100万円 – 50万円 = 50万円
法人税率は約30%前後(法人税+地方税等)
- 税金:約15万円
- 残り:35万円 → これを個人の報酬や配当などに活用可能
✅ 事業主は「使った後の利益に税金がかかる」という仕組みです。
つまり、同じ「稼ぎ方」でも結果が変わる
| 区分 | 税前に使える? | 税率(目安) | 手元に残る額(同条件) |
|---|---|---|---|
| サラリーマン | ❌使えない | 約30% | 約20万円 |
| 事業主 | ✅使える | 約30% | 約35万円 |
これは単なる節約テクニックではなく、「構造の違い」なんです。
節税=脱税ではない。合法的な選択肢を知ることがカギ
誤解しがちですが、節税とは「ズルいこと」ではありません。
国が制度として用意している正当な経費処理や優遇税制を活用することです。
たとえば…
- 法人化して外注費や広告費を経費にする
- 青色申告で特別控除(最大65万円)を受ける
- iDeCoや小規模企業共済で控除を活用する
など、知っているだけで得をする制度はたくさんあります。
私が「税」を学び始めて変わったこと
税金の仕組みを学び始めてから、私はこう考えるようになりました。
- 「高くても経費にできるなら使うべき」
- 「お金が残らないのは稼ぎ方よりも構造の問題」
- 「個人と法人で使える制度が全く違う」
そして何より、「知らなかった自分を責めず、学ぶことから始めればいい」と思えるようになりました。
まとめ|個人で稼ぐなら、税の仕組みを避けて通れない
副業や自営業に挑戦しているあなたへ。
お金を稼ぐことは大切ですが、それ以上に「お金を残す仕組み」を知ることが重要です。
知らないままだと、税金でお金が流れ続けます。
学んで行動すれば、合法的に“守る力”が身につきます。
私はこれからも、義父の事業を守りながら、副業やブログを通じて学んだことをシェアしていきます。
あなたもぜひ、「税を学ぶ」という最強の武器を手に入れてください。
それではこの辺で、ほいたらねっ👋
関連記事のおすすめ
青色申告特別控除はかなりお得!会社員×副業の活用から法人経営まで徹底解説【個人事業主と法人の違いもわかりやすく私目線に立って解説】
【2025年最新版】日本の公的保険は最強!民間保険がほぼ不要な理由を徹底解説
【保険は本当に必要?】子供保険・医療保険に入る前に考えたい「本質」と「計算」
【メリットしかない!】ふるさと納税は使わなきゃ損!私がリピートする理由とおすすめの使い方